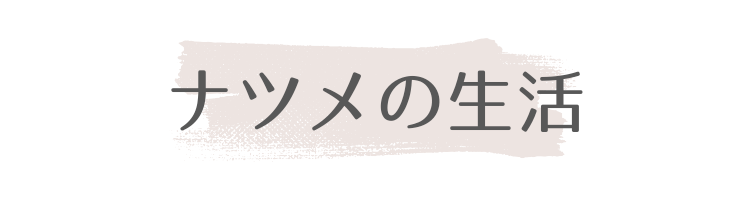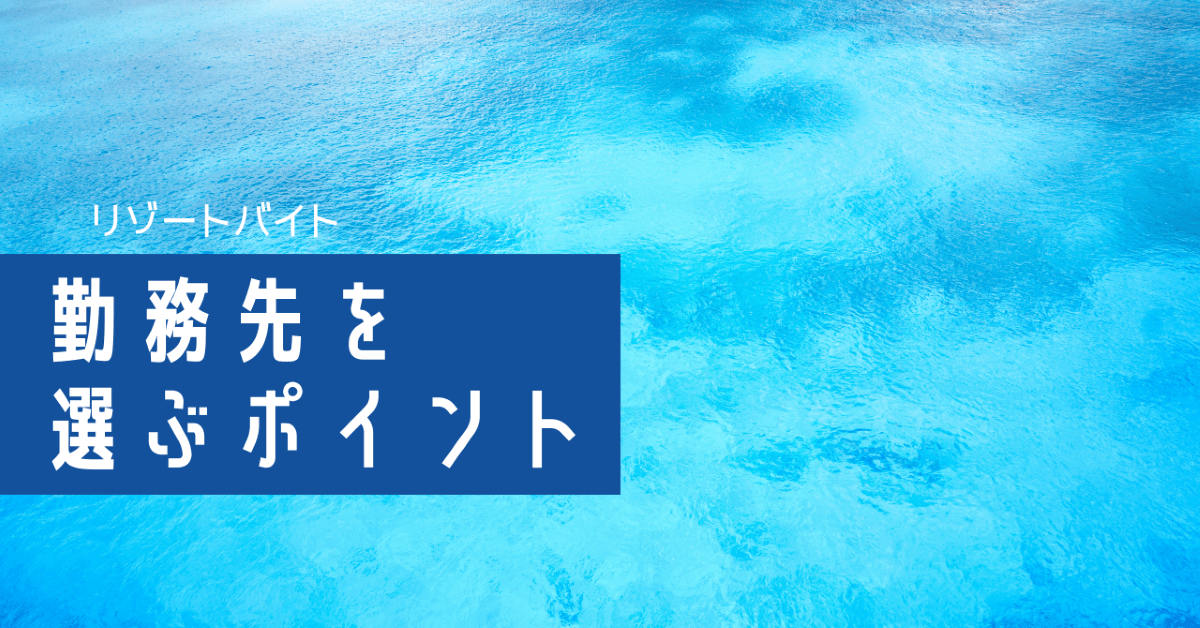今年30代にしてとうとうiDeCo(個人型確定拠出年金)を始めました。
きっかけは、住民税が上がったことでした。
デメリットはあるけれど、老後資金を銀行に預けるより増える可能性があり、住民税も下がるので、iDeCoを始めることにしました。
iDeCoでの掛金は、原則60歳まで引き出すことが出来ないので、ある程度生活防衛費を貯めて、余剰資金で行うようにしました。
生活防衛費の目安としたのは、半年生活できる金額です。万が一、働けなくても大丈夫なようにいつでも引き出せる形で貯金しています。
以前は、投資というだけで避けていたのですが、生活防衛費が貯まったこと、老後2000万円問題で投資を始める決心がつきました。
投資リスクはもちろんあるけれど、iDeCoは長期・積立・分散投資でリスクを抑えることが出来ます。
・長期運用することで、収益の振れ幅が小さくなり安定したリターンが期待できる。
・積立は、一括購入した時と比べ、毎月定額を購入し続けることで、全体として購入価格を抑えることができる。
・分散投資することで、ある1つの商品の株価が下がっても他で補完でき、1種類だけ購入の時に比べリスクを抑えることができる。
他にもiDeCoのメリットとして、
・掛金が全額所得控除の対象となる
・運用で得た利益は非課税になる
・60歳以降に受け取る時に税制優遇がある
デメリットは、
・60歳まで掛金を引き出せない
・投資信託だとマイナスになる可能性がある
・iDeCo加入・移換時、掛金納付の度に手数料がかかる
iDeCoを始める前提として、加入対象者であることを確認してから申し込みを行いました。
iDeCoは、20歳から60歳未満で条件に該当する方が加入できます。
①国民年金の第1号被保険者
②60歳未満の厚生年金保険の被保険者
③国民年金の第3号被保険者
*2022年5月からは、65歳まで加入できるようになります。
それでは私が、iDeCoを始めた流れを紹介したいと思います。
iDeCo加入の流れ
- 金融機関を決める
- 商品を決める
- 掛金を決める
- 申込用紙の提出
- 推移をみる
- 年末調整・確定申告を行う
1.金融機関を決める
iDeCoで運用できる金融機関は1社だけなので、銀行や証券会社を調べました。
選ぶポイントは、商品数の豊富さ、口座管理料や加入時手数料がかからないかです。
最終的にはどちらもよかったSBI証券に決めました。
2.商品を決める
iDeCoの商品は、元本確保商品と投資信託の2種類があります。
元本確保商品には、定期預金や保険があり、リスク(収益の振れ幅)は小さいですが、リターン(収益)も小さくなります。
投資信託には、債権、株式などがあり、元本割れする可能性がありますが、積み立てた金額よりリターンも大きいです。
私は、リスク許容度があまり高くなかったのですが、資産を少しでも増やしたかったので定期預金ではなく、投資信託を選びました。
投資信託は、3つの条件の中から選びました。
- インデックス
- 分散投資
- 信託報酬が安い
3.掛金を決める
掛金は、月5千円から加入資格によって上限額が設定されています。
私の場合、上限2万3千円でしたが、60歳まで引き出せないので、現在の給料で無理のない月2万円にしました。
ただし、iDeCoは年1回なら1000円単位で金額変更も可能なので、給料が変わった場合はまた調整しようと思います。
投資は、将来減る可能性もあるので、毎月の貯金を全てiDeCoにまわさないで、現金でもある程度は貯金するようにしています。
4.申込書の提出
会社に書いてもらう部分もあるので、提出までにすこし時間がかかりました。
5.推移をみる
申込書提出から2ヶ月ほどたって、引き落としが始まりました。
長期投資なので、一喜一憂せずに推移を見つつ、60歳近くになったら、もっとリスクの低い商品に変更したいと思います。
年末調整・確定申告の手順
iDeCoは、掛金が全額所得控除されるので、所得税、住民税が軽くなります。
所得控除の適用を受けるために年末調整か確定申告での手続きが必要になります。
〈年末調整〉
①国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届くので保管します。
②年末調整書類の「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入します。
〈確定申告〉
①国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届くので保管します。
②「確定申告書」に必要事項を記入し税務署に提出します。
今回、初回の掛金を払ったのが11月だったので、小規模企業共済等掛金払込証明書が届いたのが12月と年末調整も終わった頃でした。私は翌年2月に、確定申告をする予定です。